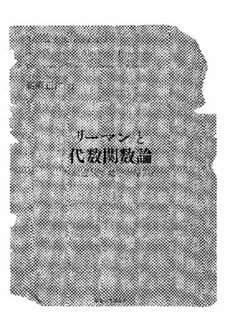Table Of ContentBernhard Riemann and the Theory of Algebraic Functions:
The Junction of Modern Mathematics in Western Europe
Masahito TAKASE
University of Tokyo Press, 2016
ISBN978-4-13-061311-8
•1•1• 1
まえがき
リーマンの名に親しみを深めたころ
数学という不思議な学問に心を寄せる者にとって, 19世紀のドイツの数学
者ベルンハルト・リーマンの名は一段と深い音色を伴って耳采に響くのではあ
るまいか.リーマンの名をはじめて知ったのはいつだったろうと自問すると,
数学に心を寄せ始めた十代の終わり掛けのころの回想へと誘われる.すでに半
世紀の昔の思い出である. リーマンに通じる道はいくつか開かれていたが,一
本の明るい道を照らしてくれたのは岡潔の晩年の一群のエッセイであった.岡
は多変数関数論の形成に大きく寄与した数学者であり,岡自身若いBにリー
マンを知ることにより数学への憧憬を深めていったのである. リーマンを語る
岡の言葉はエッセイ集の随所に散りばめられているが,次に引く言葉はひとき
わ強い印象を伴っている.
三高のとき私はアンリー・ポアンカレーの「科学の価値」をよんだ.
そうするとこういう意味のことが書いてあった.クラインはリーマン
のディリクレの原理を証明しようとして,球, ドーナツ,球に二つ耳
のついたもの,三つついたもの等の模型を頭の中で作り,それに土
の二極を置いて,頭の中で電流を流した.そしてその流れるのを見て
安心した.
リーマンというのはスイスに生れドイツのゲッチンゲンで教えた十
九世紀の大数学者,数学史中の最高峰と思うのは私だけではない.デ
ィリクレの原理というのはリーマンが発見して,その師ディリクレの
名を取って命名した大原理であって,実に簡潔,実に有力であるが,
リーマンのした見事な証明は不備であることが後にわかった.クライ
ンというのはリーマンの死後大分してゲッチンゲンの教授になったド
イツ人で,生涯リーマン一辺倒であった.
lV
私はこのポアンカレーの文章を見て限りない興味を感じた.(岡潔
『昭和への遺書敗るるもまたよき国へ』, 107-108頁)
三高というのはかつて京都に存在した第三高等学校のことで,現在の京都
大学総合人間学部の前身である.大正8年 (1919年) 9月,和歌山県粉河中
学校から三高に進んだ岡潔は,フランスの数学者ポアンカレの著作『科学の価
値』を読んでリーマンを知ったのである.岡が手にしたのは田邊元の手になる
訳書で,大正5年 (1916年) 6月に岩波書店から出版されて間もないころで
あった.岡は少し勘違いをしたようだが, リーマンの生地はスイスではなく,
ドイツのハノーファー王国のブレゼンツという村である.ゲッチンゲンとベル
リンの二つの大学で学び,ディリクレの後任としてゲッチンゲン大学の教授に
なったちなみにディリクレの前任者はガウスである.
「球 ドーナツ,球に二つ耳のついたもの,三つついたもの等」というのは
境界をもたないリーマン面,すなわち閉リーマン面の比喩的表現であり,球は
種数0, ドーナツは種数1, 球に二つ耳のついたものは種数2の閉リーマン面
に該当する. リーマン面は 1複素変数関数論の建設の場においてリーマンが
提案して全理論の根底に据えた曲面で,閉リーマン面は代数関数論の舞台であ
る.
次に引くのは岡が読んだポアンカレの言葉である.
其反封にフェリックス・クライン FelixKleinを考へると.彼は函敷
論の最も抽象的な問題の一つを研究した.即ちーの輿へられたリーマ
ン面に,輿へられた特異性を有する所の函敷が常に存在するかといふ
問題である.扱此有名な獨逸の幾何學者は如何にしたであらうか.彼
はリーマン面に置換へるに電導率が一定の法則に従つて髪化する如き
金局面を以てし,其二つの極を連結するに電池の雨極を以てした.斯
くして彼は電流が之に通じなければならぬ事,其電流の面に分配され
方が問題に要求せられた特異性を正に持つ所の函敷を定義する事を述
べたのである.(ポアンカレ『科學の債値』, 15-16頁)
まえがき v
閉リーマン面上に一定の特異性を指定し,それを許容する解析関数の存在証
明はリーマンの代数関数論の根幹である. リーマンはこれを変分法のディリク
レの原狸により証明しようとしたがその証明には瑕疵があることをヴァイエ
ルシュトラスが指摘したそれにもかかわらずクラインは金属面に電流を流す
という思考上の実験により,関数の存在を確信したのである.論理的に見て厳
密な証明とは言えず,クライン自身ももとより承知していたが,クラインは何
かしら感情の上で確実と思われるものを発見したと信じたのであろうと,ポア
ンカレはクラインの心情を付度した岡はそのようにクラインを語るポアンカ
レの文章を読んで,深遠な輿味を感じたというのである,
数学憧憬
三高から京都帝国大学に進んだ岡は,大正 12年 (1923年),京都帝大2年
生のとき友人の秋月康夫と連れ立って丸善に行き,クライン全集とエルミート
全集を購入した. どちらも全3巻の大きな書物である.クラインの全集を購
入したのはポアンカレの『科学の価値』の印象が長く尾を引いていたためで,
岡はディリクレの原理を論じるクラインの論文をこの全集で読んだ.エルミー
トはフランスの数学者で,ポアンカレの数学の師匠である.エルミートの全集
はフランス語で書かれていて,このころはまだ読めなかったが,各巻の巻頭に
添えられていたエルミートの肖像に心を惹かれた.第1巻の肖像は若い日の
エルミート.第2巻の肖像は中年のエルミート,第3巻の肖像は晩年のエル
ミート.秋月は,片手に本をもって読みふけっている中年のエルミートが気に
入って,切り抜いて額に入れ,机の上に置いた.それを見て,三高の同期生で
西田幾多郎を父にもち化学を勉強していた西田外彦が影轡を受け,丸善に駆け
つけてエルミート全集を購入し,秋月をまねて中年のエルミートの肖像を切り
取って額に入れ,机上に置いたこれに対し,岡が好きだったのは詩人の日を
しているように見えた若い日のエルミートであった.
クラインの全集ばかりではなくエルミートの全集まで買ったのもポアンカレ
の『科学の価値』の影響を受けたためで,
エルミトと語る際彼は決して眼に見える圏形を用ゐぬけれども,彼に
Vl
封しては最も抽象的の概念も生きた物に等しいといふことは人の直に
認める所であった.彼は之を見はせぬけれども.其等の概念が人為的
の集合物でなくして,何等か内的統一の原理を持つものなることを感
じて居たのである.(同上, 39頁)
という言葉に触発されたからであった.岡はこれを「エルミットの語るや如何
なる抽象的概念と雖もなお生ける如くであった」と簡潔に言い表して引用し.
秋月とともに,「この短いポアンカレーの言葉に.あ、もあろうか.こうもあ
ろうかと何時も胸を時めかせていた」(岡潔『春雨の曲』.第7稿).
ポアンカレの 1冊のエッセイは 19世紀の西欧近代の数学に遍在するロマン
チシズムをのぞき見る小さな窓であり,若い日の岡は窓辺に腰かけて. 目に映
じない何ものかを見ようとして熱いHを向けていた.そのあこがれに満ちたま
なざしが岡のエッセイを読む者の心情のカンバスにそのまま投影されて,いつ
しかリーマン,クライン,エルミート,ポアンカレの名が深く刻印されること
になったのである.
古典への回帰
岡潔のエッセイに誘われてリーマンを知ることになったが.多変数関数論の
形成過程を叙述する岡の数学論文集を読むと.岡の究極のねらいは多変数の
代数関数論にあることがはっきりと認識されて目の覚めるような思いがした.
リーマンが建設したのは 1変数の代数関数論であり.そのリーマンを憧憬す
る岡は多変数の代数関数論をめざしたのである.この事実に気づくとリーマン
の代数関数論はいよいよ解明をめざすべき大きなH標になった.リーマンと岡
を連繋する道をたどってみたいと念願するようになったのである.
日本語で書かれたテキストは多いとは言えないが.岩澤健吉の著作『代数函
数論』(岩波書店初版, 1952年.増補版, 1973年)は薦められることの多
い作品であった.巻頭に配置された長大な序文は評判が高く,代数関数論の歴
史が回想されている点に特色があった.ただし本文はこの理論の形成史とは
無関係で,歴史の流れに沿うのではなくリーマン以降に考案された様式で組み
立てられている.ヘルマン・ワイルの著作『リーマン面のイデー』 (1913年)
まえがき vii
はリーマン面を 1次元複素多様体と諒解し,その土台の上にリーマンの理論
を再構成して今日の複素多様体論の慮矢となったことで知られていた.第2
版 (1923年),第3版 (1955年)と版を童ね.第3版には英訳書も存在して
容易に入手することができた第3版に移ると大きな書き換えが行われ.初
版とは別のおもむきの作品になった.そうこうするうちに邦訳書『リーマン
面』(田村二郎訳.岩波書店, 1974年)も刊行されたが,翻訳にあたって訳者
がテキストに選定したのは初版であった.
岩澤健吉とワイルの著作はいずれも魅力的であり.心を惹かれて熱心に読み
ふけったが. この解読の試みはひんばんに頓挫して.実際にはなかなか前に進
むことができなかった. どちらの作品でも論理の連鎖が精密に組み合されて.
一歩また一歩と建築物が構築されていく. ところが.その道筋をたどり.いよ
いよ全容が日の前に現れ始めても,「代数関数論とは何か」という根本的な問
いは決して解き明かされず, どこまでも謎のままであり続けたのである.
代数関数論とは何をめざして建設された理論なのであろうか.リーマンは
「アーベル関数の理論」という大きな論文を書いて代数関数論を展開したが,
リーマン自身のねらいはどのようなものだったのであろうか.この問いに答え
るにはリーマンの理論を解説する書物を読むだけでは足らず, リーマンの論文
にいたる数学の流れを全体として把握しなければならないのではあるまいか
代数関数論の諒解がむずかしい原因は歴史にひそんでいる.今日の視点から顧
みるのではなく, リーマンに流入するリーマン以前の数学の流れを諒解し,代
数関数論の場においてリーマンが直面した諸問題の姿をリーマンとともに凝視
しなければならない.古典解読の契機がこうしてもたらされることになった.
歴史をたどる
西欧近代の数学史においてリーマンは 1個の結節点である.リーマン以前
のあれこれの流れがリーマンにおいて一堂に会してアーベル関数論に結品し,
リーマン以降に継承されてさまざまな理論に分岐していったが,本書の関心は
リーマンその人とともにリーマン以前にも注がれている.リーマンはアーベル
関数論に先立って「1個の複素変化量の関数の一般理論の基礎」 (1851年)と
いう論文を書き,今日の 1複素変数関数論の基礎理論を構築した.根幹に位
...
Vlll
置を占めるのは「関数」の概念であり,リーマンはオイラーからラグランジ
ュ コーシー フーリエを経てデイ )クレにいたる関数概念の変遷史を踏まえ
l
て独自の「関数」を提案した. しかもその変数の変域は複素数域であり, リー
マン以後いつしか「解析関数」「正則関数」などという呼称が定着した.そ
こで二つの課題が課されることになった.ひとつは関数概念のはじまりと変遷
をたどることであり, もうひとつは数学に虚量もしくは虚数を導入することの
意味を諒解することである.この二つの課題に応えようとすると,デカルト,
ライプニッツ, ヨハン・ベルヌーイ.オイラー,コーシー,ガウスと続く思索
の変遷の観察が要請される(第 1章).
虚数と関数の二つの概念が連繋すると複素関数論が生れるが, リーマンに先
立ってコーシーの複素関数論が存在した.関数の解析性の認識も必ずしも定か
とは言えず,長い年月にわたって錯綜をきわめた経緯をたどったが, コーシー
は実定積分の計算の場において留数解析を提示し, リーマンの(それにヴァイ
エルシュトラスの名をここで挙げなければならないが)複素関数論の先駆者
になった.そこでコーシーの歩みを再現することもまた意義のある課題である
(第2章).
解析関数には他の種類の関数にはない特異な属性が附随する.それは解析接
続という現象で,そのために解析関数の存在領域は関数それ自体に内在するカ
により天然自然に定まってしまう.この現象に対応するためにリーマンはリー
マン面の概念を提案し,リーマン面上で解析関数論を展開するという構想を
打ち出した. リーマン面は複素平面上に幾璽にも重なり合って広がる曲面であ
り,そこには分岐点さえ散在する. この特異なアイデアの由来を尋ねることも
大きな課題である. これを実行すると,ガウスのガウス平面のアイデアと,同
じガウスの曲面論に出会うであろう(第2章).
楕円関数論からアーベル関数論へ
リーマンは代数関数論をアーベル関数の理論と呼んだ. リーマンのいうアー
ベル関数は今日の用語でいうアーベル積分を指し,アーベル積分とは代数関
数の積分に付与された呼称である.それゆえ,関数の中でも特に代数関数の正
体を見極めることが基礎的な課題として課せられる. リーマンは代数関数とは
まえがき ix
何かという問いに対し,「閉リーマン面上の本質的特異点をもたない解析関数」
と簡潔に応じたが,関数の概念を提案し,その関数を代数関数と超越関数に二
分した一番はじめの人はオイラーである.オイラーからリーマンにいたる間に
代数関数の概念もまた変遷したのである(第1章).
アーベル関数に冠せられた形容句「アーベル」は夭折したノルウェーの数
学者の名である. 1826年秋10月,パリに滞在中のアーベルは後年「パリの論
文」と呼ばれることになる大きな論文を書き上げて,完全に一般的なアーベ
ル積分を対象にして加法定理を確立した.「パリの論文」は行方不明になった
一時期があり, 1841年に発見されてフランスの数学誌に掲載されるまで人の
目に触れることはなかったが,アーベルは超楕円積分に限定して同じ加法定
理を精密に叙述するもうひとつの論文を書いた. ドイツの学術誌『クレルレ
の数学誌」の第3巻,第4分冊に掲載されたが,その掲載誌が刊行されたの
は1828年12月3日のことであった年が明けて 1829年になり,アーベルは
4月6日に亡くなったが,ヤコビはアーベルの論文を見て加法定理を認識し,
アーベルの数学的意志を継承してそこからひとつの問題を抽出した.それがヤ
コビの逆問題であり,これを解決することがリーマンの目標になった. リーマ
ン面上の複素関数論を建設したのもそのためであった(第4章).
ヤコビの逆問題の形成過程の観察と, この問題が解けるということの意義を
明らかにすることは,本書に課せられたもっとも重い課題である.
アーベルが「パリの論文」で取り上げたアーベル積分の考察には楕円関数論
という前史が存在し,淵源をたどるとまたしてもオイラ-に出会う.オイラー
は楕円積分の加法定理を発見してこの理論に礎石を置いた人物だが,ある種の
変数分離型微分方程式の代数的積分を見つけることができずに行き詰まってい
た一時期があった.そこにイタリアの数学者ファニャノの論文集が届けられ,
オイラーが一瞥すると,探し求めていた代数的積分のひとつが記されていた.
苦境に直面していたオイラーはこれで救われて加法定理の発見に成功し,楕円
関数論の歴史が流れ始めることになった.1751年ころの出来事である.
楕円関数論のバトンはオイラーからラグランジュヘ,ラグランジュからルジ
ャンドルヘと受け継がれ,それからヤコビとアーベルの手にわたされた.アー
ベルの「パリの論文」はこの系譜の延長線上に現れたのであるから,楕円関数
X
論の形成史を諒解することは「パリの論文」.ひいてはヤコビの逆問題の真意
を理解するために不可欠の基礎作業である(第3章).
ヒルベルトの夢と岡潔の夢――多変数代数関数論の展望
ヤコビの逆問題の泉はアーベルの定理であり,そのアーベルの定理がオイ
ラーに淵源することは既述のとおりだが,数学におけるアーベルの営為に深い
影響を及ぽしたもうひとりの人物がいる.それはガウスである.
アーベルに対してばかりではなく,ガウスの影響は 19世紀の数学のほと
んど全領域に及んでいる.本書ではガウスの著作『アリトメチカ研究』 (1801
年)に端を発する数学の流れを五つまで挙げた.第 1の流れは相互法則,第
2の流れはアーベル方程式の理論,第3の流れは楕円関数の虚数乗法論であ
る.第4の流れはヤコビの逆問題であり,第5の流れはそのヤコビの逆間題
から自然に流露する多変数関数論である.これらの 5筋の流れは親密に連繋
し,ガウスが創造した「数の理論」の泄界を構成するとともに,ヒルベルトが
提示した第 12問題「アーベル体に関するクロネッカーの定理の,任意の代数
的有理域への拡張」において合流するであろう. ヒルベルトの魔法の言葉で紡
がれた夢のような予想だが,アーベル関数の理論のその先に広がる世界をヒル
ベルトに託して展望したいと思い,あらましを描写した(第5章,第 1節).
多変数関数論の一般理論を建設するのはむずかしく,ヴァイエルシュトラス
とリーマンに続いてポアンカレ,クザン,ハルトークス, E.E. レビ,ジュリ
ア,アンリ・カルタン, トゥルレンという人びとの手を経てようやく主問題が
発見され,その解決に専念した岡潔によりいくつかの果実が摘まれたころには
すでに 20世紀も半ばにさしかかっていた.一般理論は今も完成したとは言え
ないが,岡はその先に多変数代数関数論の構想を抱いて「リーマンの定理Jと
いう表題をもつ一群の研究記録を書き継いだ. リーマンはアーベル関数の理論
という名の 1変数の代数関数論の建設をめざしてまず 1複素変数関数の基礎
理論を構築したが,岡の心には若い日にポアンカレのエッセイを読んでリーマ
ンに親しみを深めた体験が生涯を通じて生き続け,多複素変数の世界において
リーマンの歩みにならおうとしたのである(第5章,第2節).ヒルベルトの
夢と二幅対を構成する岡潔の夢がここにわずかに顔をのぞかせている.